あきた伝統野菜について
コンテンツ番号:9964
更新日:
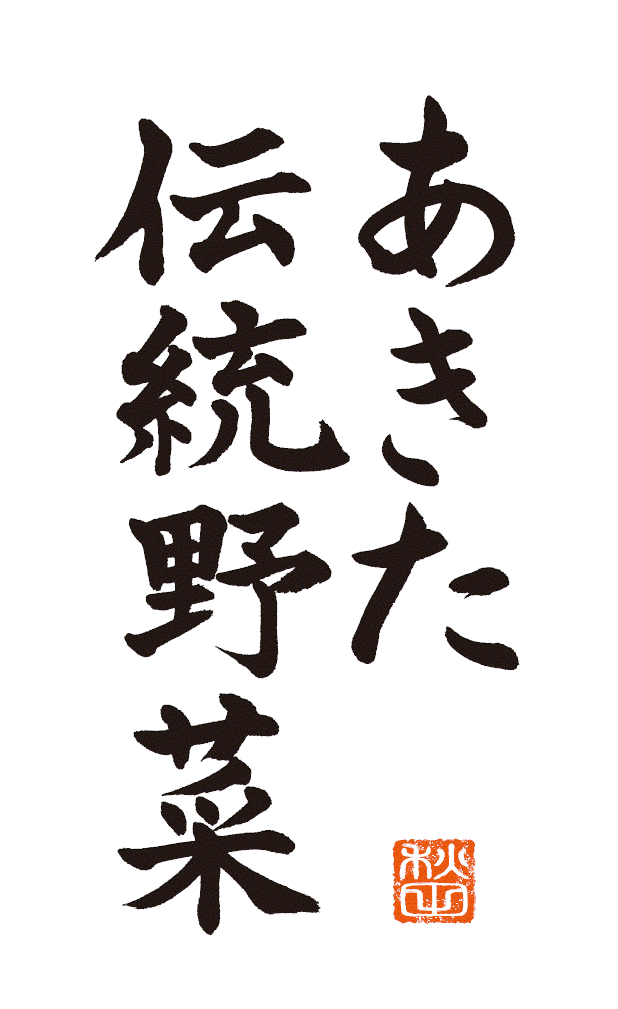
秋田県には地名や人名、形状や栽培方法を冠した独自の伝統野菜があります。
それぞれ長い歴史を持ち、地域の食文化を形作ってきました。
これらは、品種の特徴だけではなく、気象や土地条件、栽培技術などによって、その土地固有の味として伝えられてきたものです。しかし、その多くは、栽培が容易で収穫量が多い改良種に押されて、徐々に栽培者が少なくなっています。
秋田の食を彩る伝統野菜の魅力をもう一度見直し、豊かな秋田の食材として伝えていきましょう。
「秋田の伝統野菜とは」
次の三つの事項を満たす品目としています。
- 昭和30年代以前から県内で栽培されていたもの。
- 地名、人名がついているなど、秋田県に由来しているもの。
- 現在でも種子や苗があり、生産物が手に入るもの。
春 ひろっこ 秋田さしびろ 仁井田菜 亀の助ねぎ 貝沢ふくだち菜 秋田ふき
夏 じゅんさい 阿仁ふき 五葉豆 八木にんにく 関口なす 仙北丸なす 新処なす 富沢なす
秋 湯沢ぎく 雫田カブ てんこ小豆 とんぶり カナカブ 平良カブ 横沢曲がりねぎ 石橋ごぼう 大館地大根
秋・冬 松館しぼり大根 仁井田大根 三関せり 山内にんじん からとり芋 ちょろぎ 田沢ながいも
※品目名をクリックすると、該当品目の項目にジャンプします。
「あきた伝統野菜」振興指針
「あきた伝統野菜」の現状や課題を共有し、関係機関・団体の共通の理解のもとに今後の方向性を明らかにし、県全体の取組として展開していくため、「あきた伝統野菜」振興指針を策定しました。
・「あきた伝統野菜」振興指針(令和3年11月策定) [4218KB]
「あきた伝統野菜」パンフレット
令和4年3月に「あきた伝統野菜」39品目を紹介したパンフレットを制作しました。
各伝統野菜の特徴を紹介します。
「食べ方」のアンダーライン付きの料理名をクリックするとレシピに移動します。
ひろっこ
- 収穫時期
12月~4月 - 栽培地
湯沢市 - 栽培方法
8月下旬~9月上旬に植え付けし、12月に入り、積雪後まもなく収穫を開始する。
収穫は雪融け直前まで行われる。 - 特徴
あさつきの若芽。雪の下で萌芽した白い芽を、深い雪を掘り収穫する。雪の下で糖度が増す、早春の味の代表格。
雪消え後の青い若芽も、青ひろっことして食する。大正時代に、旧須川村から栽培が始まったとされる。

- 食べ方
ひろっこかやき、ひろっこの酢味噌和え
秋田さしびろ(あきたさしびろ)
- 収穫時期
2月~5月 - 栽培地
秋田市、由利本荘市 - 栽培方法
8月下旬~9月上旬に、株分けして植え付ける。雪融け後、トンネルを設置し、生育を促す。 - 特徴
越冬性の高い加賀群の分けつねぎ。甘みとつるりとした食感を楽しむ。
地際から刈り取り収穫し、鍋ものや汁もの、卵とじ、酢みそ和えなどに利用する。
.png)
- 食べ方
鍋もの、汁もの、酢みそ和え
仁井田菜(にいだな)
- 収穫時期
2月~4月 - 栽培地
秋田市 - 栽培方法
9月初旬に播種。越冬させ、再度、生長してくる4月以降に収穫。
春一番に収穫できる野菜として栽培されている。 - 特徴
越冬性の高い漬け菜の一種。雪の下で蓄えた養分で、雪融けと同時に一気に成長する。
わずかに苦みを持つ味の濃い青菜で、おひたしや炒め物などに向く。

- 食べ方
おひたし、炒め物他
亀の助ねぎ(かめのすけねぎ)
- 収穫時期
3月~5月 - 栽培地
大仙市 - 栽培方法
4月上旬に播種、6月下旬に定植。秋どりも可能であるが、越冬させ、春に収穫する。 - 特徴
柔らかく、甘さと香りが格別の春ねぎ。
昭和初期に地元篤農家の石橋氏が、砂村系のねぎから育成した。
耐寒性が強く越冬率が高いため、4~5月に収穫するねぎとして利用されている。

貝沢ふくだち菜(かいさわふくだちな)
- 収穫時期
4月~5月 - 栽培地
羽後町 - 特徴
古くから栽培されてきた露地栽培のふくだち(とう立ち野菜)。
雪消え後の4~5月に収穫し、おひたしや漬物として食される。
わずかに苦みがあり、甘みを強く感じる。

秋田ふき(あきたふき)
- 収穫時期
6月 - 栽培地
鹿角市、秋田市 - 特徴
江戸時代から栽培されており、葉の直径1~1.5m、草丈2mにもなる日本一大きなふき。
漬物、砂糖漬け、煮物に用いられ、観光資源としても知られる。
秋田市では仁井田地区に数戸、鹿角市では転作田や家の庭先などに数多く植えられている。

じゅんさい
- 収穫時期
6月~7月 - 栽培地
三種町 - 栽培方法
自然池沼や古い灌漑用ため池、転作田において、水深50~80cm程度の水域に生育している。
4月~5月にかけて水底の地下茎から新芽が伸び、夏にはハスの葉のように水面いっぱいに浮葉を広げる。
地下茎から伸びたヌメリと呼ばれる透明な粘質物のある幼葉や葉柄の部分を食用としている。 - 特徴
スイレン科ジュンサイ属の多年草で独特の食感が珍重される。
森岳地区の天然沼から、転作田で栽培されるようになり日本一の産地となった。
都道府県によっては絶滅危惧種となっている。

- 食べ方
じゅんさい鳥鍋、じゅんさい三杯酢、じゅんさいそば
阿仁ふき(あにふき)
- 収穫時期
6月~7月 - 栽培地
北秋田市 - 特徴
葉柄が青々として美しく、繊維や苦みが少ないため、食味と食感に優れる京ふき系のふき。
県農業試験場が育成した、葉柄が長く太い品種「こまち笠」が栽培されている。

- 食べ方
炒め物、鍋物、煮付ほか
五葉豆(ごようまめ)
- 収穫時期
8月~9月 - 栽培地
県南部 - 栽培方法
通常のえだまめと同様 - 特徴
古くから伝わる在来種のえだまめで、自家用として栽培されている。
五枚葉が特徴で、香りと甘みが強く食味の良い品種。「あきた香り五葉」の育種に活用された。


八木にんにく(やぎにんにく)
- 収穫時期
6月~10月 - 栽培地
横手市 - 栽培方法
通常のにんにくと同様 - 特徴
横手市増田町の八木集落に伝わるにんにく。
とう立ちがなく、植付け適期の幅が広く、貯蔵中も出芽しにくい。皮に赤みがあるのも特徴。
青にんにく(6月のみ)として生食や漬物に、十分に肥大したものは風味付けとして利用される。

- 食べ方
青にんにくで生食、すりおろして薬味
関口なす(せきぐちなす)
- 収穫時期
7月~10月 - 栽培地
湯沢市 - 栽培方法
通常のなすと同様 - 特徴
江戸時代から湯沢市関口地区を中心に栽培されている丸なす。
たくさんの実をつけ、色、形、食感が抜群で漬物に適する。
皮はやや堅く果肉は締まっていて、わずかに苦みがあり、ヘタの下が真っ白なのが特徴。

仙北丸なす(せんぼくまるなす)
- 収穫時期
7月~10月 - 栽培地
大仙市 - 栽培方法
通常のなすと同様 - 特徴
秋田のなすを代表する鮮やかな紺色をした丸なす。
玄米と麹で漬ける「なすのふかし漬け」に用いられる。
紺色が鮮やかで、果皮・果肉がしっかりしており、塩蔵しても果肉が水分を含みにくいことから、長期保存用の漬物に利用される。

- 食べ方
ふかしなす、なすのオムレツ
新処なす(あらところなす)
- 収穫時期
7月~10月 - 栽培地
横手市 - 栽培方法
通常のなすと同様 - 特徴
横手市十文字町新処集落に伝わる巾着型のなす。肉質は密で張りがある。
中程度の大きさで上下を切り落として塩蔵し、菊が出る晩秋に「なすの花すし」に漬け直しをする。

- 食べ方
花すし、カルパッチョ仕立て
富沢なす(とみざわなす)
- 収穫時期
7月~10月 - 栽培地
横手市 - 特徴
主に漬物用、特に紋漬け(菊の花ずし)用として栽培され、増田や十文字地域の朝市で販売されてきた。
果形は卵形で、湯沢市の関口なすと類似しており、系統が近いことが確認されている。

小様きゅうり(こざまきゅうり)
- 収穫時期
7月~9月 - 栽培地
北秋田市 - 特徴
北秋田市阿仁小様地域に伝わる地うりで、切り口が三角形になる。瑞々しく、張りがありやや苦みを持つ。
阿仁鉱山の労働者の水分補給に利用され、市日などで販売されてきた歴史を持つ。
一度途絶えたが、平成23年から復活している。

- 食べ方
冷やし汁
田沢地うり(たざわじうり)
- 収穫時期
7月~9月 - 栽培地
仙北市 - 特徴
古くから仙北市田沢地域や桧木内地区において、自家採種により栽培されてきた地うり。
生食のほか、漬物やきゅうりもみ、冷やし汁などに利用されてきた。
田沢地域では秋田杉の山林作業に携行され、その元山守によって栽培され続け、守られてきた。

- 食べ方
冷やし汁
仁賀保秋スイカ(にかほあきすいか)
- 収穫時期
8月~9月 - 栽培地
にかほ市 - 特徴
お盆過ぎから、9月中旬の稲刈りが始まる頃まで収穫されるすいか。
瑞々しい触感とさっぱりした糖度で、農作業の合間に喉を潤すのに適するとして好まれ、栽培が継続されてきた。

えつり赤にんにく(えつりあかにんにく)
- 収穫時期
6月~7月 - 栽培地
大館市 - 特徴
江戸時代中期、餌釣地区へ移り住む際に持ち込まれたとみられ、同地区で代々増殖されてきた。
保護葉の色が赤紫色で、辛みが強く、にんにくの風味も強い。
.png)
湯沢ぎく(ゆざわぎく)
- 収穫時期
7月~10月 - 栽培地
湯沢市 - 栽培方法
5月初旬に植え付け。7月20日頃から収穫開始。 - 特徴
昭和20年代に在来菊の中から食味の良い物を選抜し、食用菊として定着した。
早生で夏菊の特性を持ちながらも、霜が降りるまで出荷できる、花付きのよい長期出荷の菊。
鮮やかな色味と香りの良さが特徴。

- 食べ方
菊の花の味噌漬け
雫田カブ(しずくだかぶ)
- 収穫時期
4月・9月~10月 - 栽培地
仙北市 - 栽培方法
8月末~9月初旬に播種し、越冬させ、雪融け後の4月末に収穫。 - 特徴
仙北市角館の野田集落と雫田集落周辺で栽培されるかぶ。こぼれ種で自生するほど生命力が強い。
ゴツゴツとした表面は野生的で、わさびにも似た風味の刺激がある。漬物として利用する。
越冬させることで風味、辛みがでる。

- 食べ方
漬物
てんこ小豆(黒ささげ)(てんこあずき)
- 収穫時期
8月~10月 - 栽培地
県内全域 - 特徴
「てんこ(天向、天甲等)小豆」は、県南では「ならじゃ豆」とも言われ、赤飯には欠かせないささげ。
お祝いの赤飯のほか、仏事の黒飯に用いられる。
小豆は崩れ易く胴割れすることから、縁起を担ぐため黒ささげを使ったと言われている。

- 食べ方
赤飯
とんぶり
- 収穫時期
9月~11月 - 栽培地
大館市 - 栽培方法
4月20日以降に播種され、育苗後、定植される。土寄せや芯止め等の作業を行い、9月から収穫が始まる。 - 特徴
大館市が生産量日本一を誇り、「畑のキャビア」と呼ばれる。
アカザ科のホウキグサの実を、地域にのみ伝わる独自技術で加工することで、初めて食用となる。
加工品は通年で流通している。

- 食べ方
とんぶりかんたんレシピ
カナカブ
- 収穫時期
10月~12月 - 栽培地
にかほ市、由利本荘市 - 栽培方法
8月に山焼きされた畑に播種。10月から収穫が始まる。 - 特徴
古くは焼き畑で栽培された在来種で、洋種系の白長かぶ。
焼畑や普通畑で栽培され、根形も短太から長形まで様々な形があり、主に酢漬けにして食される。
サクサクとした歯触りで、辛みなどの風味がある。

- 食べ方
カナカブ漬け
平良カブ(たいらかぶ)
- 収穫時期
11月~12月 - 栽培地
東成瀬村 - 特徴
古くから平良地区でのみ栽培されてきた、在来種の青首の長かぶ。
肉質は緻密、パリパリとした歯触りで食感が良く、風味が強い。
麹漬けにして食される。

- 食べ方
漬物
横沢曲がりねぎ(よこさわまがりねぎ)
- 収穫時期
10月~11月 - 栽培地
大仙市 - 栽培方法
6月頃苗床に播種し、生育させ、そのまま越冬。翌年5月に本畑に1回目の植替え。
8月に2回目の植替えを行う。その際に根部を曲げて土を寄せる。10月中旬頃から収穫が行われる。 - 特徴
大仙市太田の横沢地区に伝わる在来種で、2年かけて栽培される。植え替え時に、寝かせて植えることで曲げて風味を出す。
柔らかく、香り成分のアリシンが多く含まれ、青ねぎ、白ねぎともに食する。
江戸時代に、久保田城主 佐竹氏から伝授されたとの言い伝えがある。

- 食べ方
薬味、鍋物等
石橋ごぼう(いしばしごぼう)
- 収穫時期
10月~11月 - 栽培地
大仙市 - 栽培方法
通常のごぼうと同様。 - 特徴
昭和30年に大仙市の篤農家 石橋氏が育成した早生品種。茎が赤く、葉はやや小さい。
根は長くて肉付き良く、白肌・白肉で風味の良さに定評がある。

- 食べ方
きんぴらがおすすめ。柔らかいので長く煮込む料理は不向き。
大館地大根(おおだてじだいこん)
- 収穫時期
10月~11月 - 栽培地
大館市、北秋田市 - 栽培方法
播種は8月下旬頃。10月中旬頃に収穫期を迎える。栽培管理は通常の青首だいこんと同様。 - 特徴
大館・北秋田地域に伝わるだいこんで、地元では「かたでご」と呼ばれる。
硬い肉質で歯触りが良く、保存性の高いたくあんになる。辛みだいこんとしても活用される。
赤首、白、など系統によって形や色が異なる。

- 食べ方
たくあん漬け、薬味
山内せり(さんないせり)
- 収穫時期
8月~11月 - 栽培地
横手市 - 特徴
9月に収穫最盛期を迎える早生せり。冬期に酒蔵などに働きに出る農家で栽培されてきた。
在来種から選抜され、やや標高がある山間部での栽培に適する。
遮光により、強い日差しを避けるなどの工夫をして栽培されている。

秋田霜降りささげ(あきたしもふりささげ)
- 収穫時期
9月~10月 - 栽培地
仙北市ほか県内各地 - 特徴
特に仙北地域で栽培され、寒さに強く霜が降りる頃まで食されることから、「霜降りささげ」と呼ばれる。
莢に黒い筋状の斑があり、熱を通すと斑が消え、鮮やかな緑色になる。

沼山だいこん(ぬまやまだいこん)
- 収穫時期
10月~11月 - 栽培地
秋田市、潟上市、大仙市 - 特徴
横手市沼山集落で栽培されてきた青首だいこん。
首が鮮やかな緑色で、水分は少なく肉質硬めで、独特な風味がある。
かつては沼山集落から山内地域で「青頭」と呼ばれ栽培されてきた。現在は、県内数か所で栽培されている。

エゴマ(えごま)
- 収穫時期
10月~11月 - 栽培地
大館市、八峰町、由利本荘市、東成瀬村 - 特徴
奈良時代の秋田城跡からも発掘されており、「つぶあぶら」や「じゅうねん」と呼ばれ、古くから食用と灯火用として、県内全域で栽培・利用されてきた。
近年の健康志向からエゴマが見直され、栽培が拡大している。

地タカナ(じたかな)
- 収穫時期
11月 - 栽培地
仙北市 - 特徴
古くから仙北地域で漬け菜用として栽培されてきた。
全国で栽培されている「たかな」とは全く違う品種で、小ぶりで葉と根を食べる。
辛みなどの強い風味があり、麹漬けや味噌漬けなどで食される。

松館しぼり大根(まつだてしぼりだいこん)
- 収穫時期
11月~3月 - 栽培地
鹿角市 - 栽培方法
9月初旬に播種し、10月中旬から収穫。 - 特徴
鹿角市松館集落で百年以上前から栽培されてきた地だいこん。
水分が少なく肉質は密、おろし汁の辛み成分(イソチアシアネート)が多く、日本一辛いだいこんと言われている。
おろし汁は、そばや刺身の薬味として用いられる。

- 食べ方
湯豆腐や肉料理の薬味、一夜漬け
仁井田大根(にいだだいこん)
- 収穫時期
10月~11月 - 栽培地
秋田市 - 特徴
秋田市の台所とも呼ばれ古くからの野菜産地である仁井田地区で栽培されてきた。
緻密な肉質、独自の歯切れと強い風味でたくあん用として使用される。
生産者の高齢化などによって栽培が激減している。

- 食べ方
漬物
三関せり(みつせきせり)
- 収穫時期
9月~3月 - 栽培地
湯沢市 - 栽培方法
露地栽培と雪よけのためビニールハウスでも栽培されている。
ビニールハウスの場合は、9月上旬に植え付けし、冬期間に収穫する。 - 特徴
年間を通じて清流水に恵まれている湯沢市三関地区で、江戸時代から栽培されている。
三関地区の在来種から選抜淘汰され、品種名は「改良三関」。葉や茎が太く、根が白く長いのが特徴。
秋田の鍋物には欠かせないものとなっている。

- 食べ方
セリ焼き、きりたんぽ鍋
山内にんじん(さんないにんじん)
- 収穫時期
10月~12月 - 栽培地
横手市 - 特徴
昭和20年代に横手市山内地区で選抜された品種。
長さが30センチ以上と太くて長く、鮮やかな赤色で肉質がしっかりしたにんじん。
パリッとした食感と強い甘みが特長で、漬物、サラダ、煮物に向く。一時栽培者が激減したが、復活している。

- 食べ方
揚げ物、きんぴらがおすすめ。肉質がしまっているため煮崩れしにくいので、煮物にも向く。
からとり芋(からとりいも)
- 収穫時期
9月~11月 - 栽培地
由利本荘市、にかほ市 - 特徴
さといもの一種で葉柄(ずいき)と親芋を食する。
葉柄はいがらさが少なく食味が良い。芋は独特のとろりとした食感と甘さがある。
畑や水を張った苗代で栽培され、青茎と赤茎がある。

- 食べ方
親芋、小芋は煮物。ずいきは酢の物等
ちょろぎ
- 収穫時期
10月~11月 - 栽培地
湯沢市 - 特徴
シソ科の宿根草で、「長老喜」、「千代呂木」などの字があてられる縁起物食材。地下茎の先端部が渦巻き状の形になる。
サクサクとした歯触りを活かして、梅しそ漬けなどの漬物にされ、正月の黒豆に添えられる。

- 食べ方
ちょろぎの漬物
田沢ながいも(たざわながいも)
- 収穫時期
10月~11月 - 栽培地
仙北市 - 特徴
田沢地区に伝わる田沢ながいもから、県内の育種家が系統選抜した「田沢一号」が栽培されている。
地域の土壌条件ともよく合うため、芋は白く、コクとほどよい粘りがある。
とろろ芋に最適。

- 食べ方
とろろ芋など
